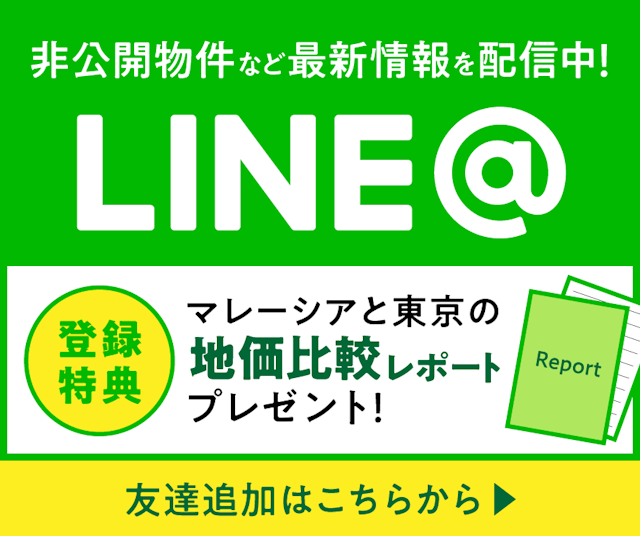「年収〇〇円超えたら資産管理会社を作った方がいい」などの話を聞き、資産管理会社の設立に興味を持たれている方は多いでしょう。本記事では、そんな資産管理会社の基本やメリット・デメリットなど、気になる疑問を解消していきます。
「年収〇〇円超えたら資産管理会社を作った方がいい」などの話を聞き、資産管理会社の設立に興味を持たれている方は多いでしょう。本記事では、そんな資産管理会社の基本やメリット・デメリットなど、気になる疑問を解消していきます。
資産管理会社に興味を持たれているサラリーマンや個人投資家の方必見です。
資産管理会社とは? わかりやすく解説
資産管理会社とは、社長となるサラリーマンや個人投資家といった方が、不動産や株式などの保有資産を管理する目的で設立する会社のことです。
通常、会社というものは営利目的で設立され、事業を通じて利益を得たり、株主から資金調達を行なったりします。一方、資産管理会社は営利目的ではなく、あくまで「保有資産を管理すること」が目的です。
そうした目的で設立した会社を「プライベートカンパニー」と呼ぶこともあります。ただし、プライベートカンパニーは資産管理だけでなく、副業収入の節税対策なども目的としているので、厳密に言えば資産管理会社とは違います。
2006年5月に新会社法が施行されたことにより最低資本金制度が撤廃され、資本金が1円でも会社が設立できるようになりました。これに伴い、個人の保有資産を管理するための会社設立に注目が集まり始め、今では資産運用を行なっているサラリーマンや個人投資家の中では、一般的になりつつあります。
資産管理会社を設立すべき人の特徴
資産管理会社の設立はどういった人に向いているのか?ここではその特徴をご紹介しますので、ご自身に当てはまるかどうか確認しながら読み進めていただければと思います。
不動産投資などを行なっているサラリーマン
不動産投資や株式投資を行なっているサラリーマンの方は、それぞれ所得として確定申告をする必要があります(株式投資などを特定口座で行なっている場合は不要)。
給与所得と合わせてある程度大きい金額を得ている場合は、所得税がその分大きくなるかもしれません。したがって資産管理会社を設立する方が、最終的な納税額が安くなるかもしれないのです。
不動産などを所有している個人投資家
不動産などを所有している個人投資家に関しても、同じことが言えます。不動産所得は総合課税なので、他の所得と合算した金額から税額を計算します。
つまり、多額の不動産所得を得ている場合は最大45%の所得税が課税されるかもしれないのです。一方、資産管理会社を通じた所得なら法人税が適用され、実効税率は30.26%のため、所得税として課税されるよりも安く済むかもしれません。
相続税を節税したい資産家
日本では遺産相続において、遺産評価額に応じて最大55%の相続税が課せられます。遺族に少しでも資産を残したいと考える資産家の場合、資産管理会社を設立する方が相続税を抑えられる可能性があります。
資産管理会社を設立し、家族を役員にすれば役員報酬を資産で支払うことができるため、相続税の課税対象から外れるケースがあるのです。
自社株相続を考えている経営者
相続人に対して自社株の相続をする場合、普通株式を相続してしまうと会社の経営方針に関するトラブルが起きた際に、意見統一が難しくなるケースがあります。
そこで、資産管理会社において普通株式と無議決権株式を発行し、後継予定者へ普通株式を相続、それ以外の相続人には無議決権株式を相続させることでトラブルを回避できます。
資産管理会社はいくらから設立すべきか
資産管理会社の設立を検討されている方の多くは、「年間所得がいくらから設立すべきか?」と悩んでいることでしょう。
1つの目安になるのが「年間所得800万円」という数字です。年間800万円の所得を得ている場合、所得税率は23%となります。一方、資本金1億円以下の中小企業の場合、年間所得が800万円以下の部分については、15%の法人税が課せられます。(適用除外事業者は19%)が課せられます。
つまり、所得税と法人税を比較すると、8ポイントもの差があることになるのです。また、所得税は累進課税なので年間所得が900万円を超えると33%が適用され、法人税の実効税率を上回ります。したがって「年間所得900万円」を2つ目の基準として設定することができますね。
実際は所得から基礎控除やその他さまざまな控除を行った上で税額が決定するため、「自分が資産管理会社を設立したらどれくらいの節税効果があるのか?」ということに関しては、税理士に相談することをおすすめします。
参考:国税庁「所得税の税率」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
国税庁「法人税の税率」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm
資産管理会社を設立する4つのメリット
続いて、資産管理会社を設立する代表的なメリットをご紹介します。不動産や株式などの資産運用を行なっているサラリーマンや個人投資家にとって、大きなメリットがあるので確認していきましょう。
所得を分散できる
資産管理会社を設立することで、家族を役員に任命し、役員報酬の支払い所得を分散することができます。役員報酬は経費として計上でき、なおかつ支払を受ける家族にのみ控除が適用されるので、高い節税効果が期待できます。
もちろん、家族がいない方でも資産管理会社を設立することで節税効果は大きいケースが多々あります。
個人事業主よりも経費項目が多い
資産管理会社などの法人は、個人事業主よりも幅広い経費項目が認められています。法人では給与や賞与も経費として計上できるため、前述のように家族を役員に任命すると節税効果があるのです。
また、退職金や出張手当、社宅などを経費として計上できるため、個人事業主よりも圧倒的に広い範囲で経費項目を使い、税金対策につなげられます。
オーナーは厚生年金保険に加入できる
個人投資家の場合、資産管理会社を設立すると厚生年金保険に加入する資格を得られます。国民年金に比べると厚生年金の方が金額が大きくなってしまうケースがありますが、その分受給額も国民年金より大きくなることが多々あります。
<日本年金機構が発表した国民年金と厚生年金の受給額>
|
令和4年度(月額) |
令和3年度(月額) | |
|---|---|---|
| 国民年金(老齢基礎年金(満額)) | 64,816円 | 65,075円 |
| 厚生年金※(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) | 219,593円 | 220,496円 |
※均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準
安定的に経営権を確保できる
上場企業の場合は、資産管理会社を設立し、経営者一族が保有している株式を資産管理会社に持たせることで安定的に経営権を確保できるというメリットがあります。
親族は一般的に安定株主と呼ばれますが、上場後に株を売却してしまい、経営者一族が会社の実権を握れなくなるリスクがあります。
一方で、資産管理会社の一族保有の株式を持たせれば、親族であっても簡単には株式を売却できません。
資産管理会社は「株式会社」と「合同会社」どっちが有利?
次に、資産管理会社を株式会社で設立するか?合同会社で設立するか?という悩みに言及していきます。
相続を視野に入れるなら株式会社
株式会社は「出資者≠経営者」という形態の法人なので、上場しない限りは経営者が会社の実権を握ることになります。つまり、親会社や外部から出資を受けていない中小企業のほとんどは、経営者が裁量を持っています。
資産管理会社で管理している資産の相続を視野に入れているのならば、株式会社を選びましょう。合同会社は「出資者≒経営者」という形態の法人であり、執行役員の過半数の決定がなければ業務執行ができません。
信頼を置いている親族であっても、相続直前になって意見を変えてしまう可能性もあります。すると複雑なトラブルに発展してしまうので、これを事前に避けるためにも株式会社での設立をおすすめします。
株式会社なら金融機関からの信用も得られる
株式会社で設立するもう1つのメリットは、「金融機関からの信用が得られる」ということです。合同会社に比べて守るべき法規制が多く、登記費用も高くなります。
また、社会的知名度が高いのは圧倒的に株式会社なので、必然的に信用度が高くなるのです。資産運用を行う上で、あるいは新しい事業を立てる際には金融機関からの融資が必要な場合があります。
これを考慮すると、株式会社で設立する方が金融機関からの信用が得られ、融資を受けられる可能性が高くなるのです。
設立コストを抑えるなら合同会社
一方で、「相続の予定はまだまだない、事業を立てるつもりもない、とにかく登記費用を安く抑えたい」という場合は、合同会社での設立をおすすめします。
合同会社と株式会社では、登記費用に約15万円ほどの差が生じます。また、株式会社では決算公告が義務付けられており、これにかかる税理士費用などで合同会社よりも法人維持費用が高くなります。
「資産管理会社の設立コストも維持コストも抑えたい」という方の場合は、合同会社での設立を優先的に検討しましょう。
資産管理会社を設立する際のデメリットと注意点
資産管理会社の設立には魅力的なメリットがありますが、デメリットもあります。ここでは資産管理会社のデメリットと注意点をご紹介しますので、設立検討時の参考にしてください。
設立・維持には費用がかかる
資産管理会社の設立には、どの法人形態であっても設立と維持の費用がかかります。
<設立費用>
| 株式会社 | 合同会社、合資会社、合名会社 | |
|---|---|---|
| 定款認証 | 3万~5万円 | 不要 |
| 定款の収入印紙 | 4万円(ただし、電子定款の場合は不要) | |
| 定款の謄本手数料 | 2,000円 | 不要 |
| 登記費用 | 15万円 | 6万円 |
| 合計 | 18万2,000円~24万2,000円 | 6万円または10万円 |
<維持費用>
| 株式会社 | 合同会社、合資会社、合名会社 | |
|---|---|---|
| 住民税均等割 | 7万円 | |
| 社会保険料 | 給与支払額に対して一定割合 | |
| 税理士費用 | 20~50万円 | |
| 決算公告費用 |
官報に掲載:約7万5,000円~ 新聞に掲載:10~100万円 Webサイトに掲載:0円 |
不要 |
| 役員変更登記費用(司法書士への依頼費用含) | 1~7万円 | 不要 |
| 株主総会 | 規模により異なる | 不要 |
資産管理会社を設立する際は、こうした設立と維持の費用を支払う意義があるかどうかを、慎重に検討する必要があります。
赤字でも法人住民税はかかる
「資産管理会社を設立し、赤字計上すれば税金がかからない」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。
上記の表にある「住民税均等割」という税金は、たとえ利益がゼロでも支払わなければいけません。つまり、最低でも7万円の税金額が発生するため、こちらも考慮した上で資産管理会社を設立するかを検討しましょう。
資産運用で利益が出ないと節税にならない
資産管理会社で高い節税効果が期待できるのは、資産運用によって利益が出ている場合です。たとえば、不動産などの資産を会社に持たせたからといって、固定資産税が安くなるといった制度は存在しません。
つまり、資産運用で一定の利益が出ていない方の場合は、資産管理会社を設立しても設立コストや維持費用が、節税効果を上回ってしまうケースもあるので注意してください。
資産管理会社をご検討の方は、まずは専門家に相談を
資産管理会社を設立するにあたって大切なことは、現状把握と節税に関する確かな知識、そして実行力です。
サラリーマンや個人資産家の方で、節税対策について深い知識を持たれている方は、そう多くはありません。「個人で資産管理会社を設立して損をした」というケースは数えきれないほどありますので、まずは深呼吸して立ち止まりましょう。
少しでも資産管理会社が気になる方は、まずは資産運用の節税対策に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
本記事では、資産管理会社の基本やメリット・デメリットなどをご紹介しました。資産管理会社は現在大きなトレンドになっており、注目の節税スキームです。しかし、デメリットや注意点もあることを忘れないでください。